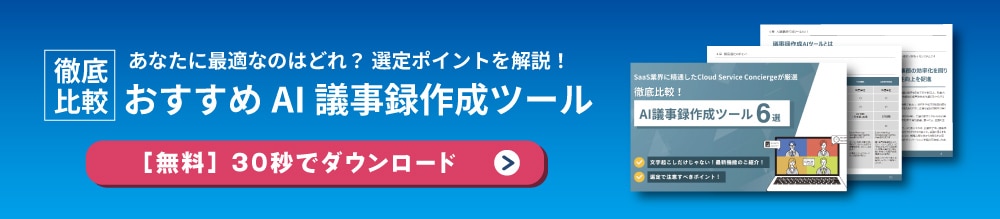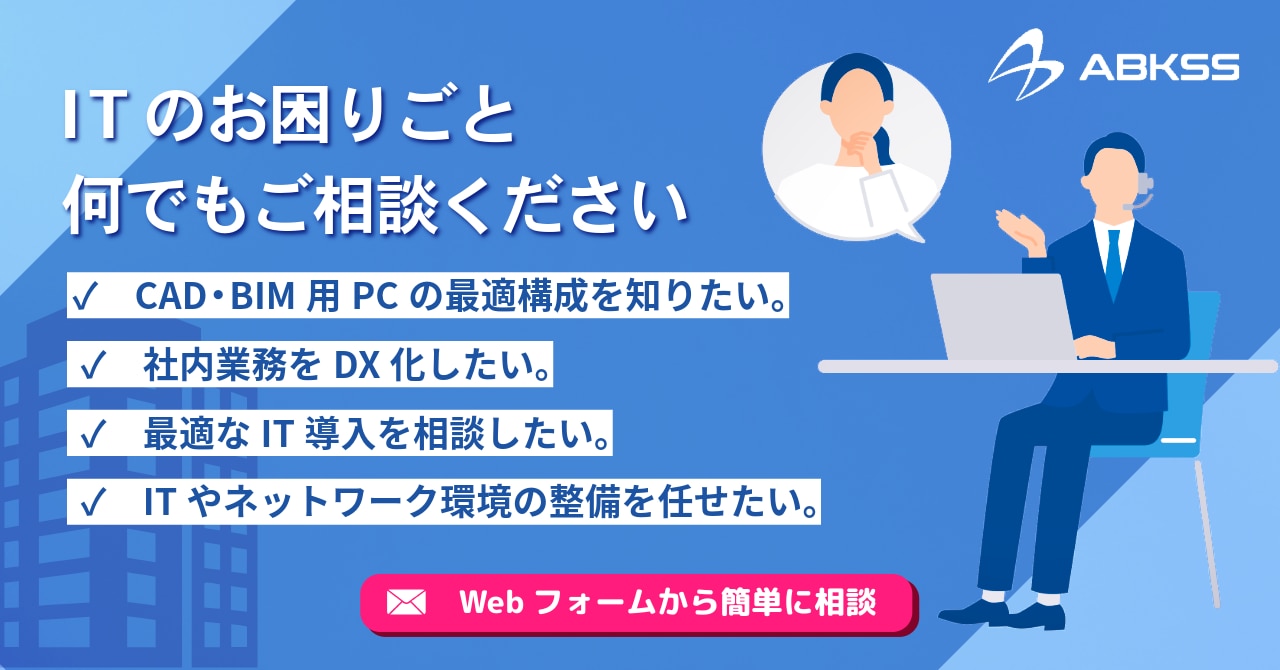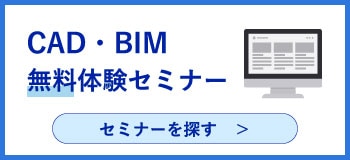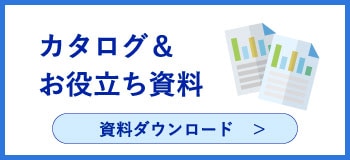AI文字起こしツールおすすめ10選!導入メリットや活用例を徹底解説

近年、AI技術の進歩に伴い、音声や動画を簡単かつ正確にテキスト化できるようになりました。
テレワークの普及やWeb会議の増加により、議事録作成や情報の共有がこれまで以上に求められる時代となっています。そんな中、手間をかけずに高精度な文字起こしを実現できる「AI文字起こしツール」が、多くの企業や個人に注目されています。
本記事では、AI文字起こしツールの10選をはじめ、導入するメリットや活用事例、注意点などを総合的に解説します。効率化のヒントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
このような方におすすめの記事です
- 音声データや記録の変換作業に時間がかかってしまう方
- AI文字起こし技術について詳しく知りたい方
- AI文字起こしツールを検討している方
▼あわせてよく読まれている資料
この記事で紹介しているAI議事録作成ツールの詳細比較や選定ポイントをまとめた資料をご用意しました。 無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
目次[非表示]
- ・AI文字起こしとは?
- ・導入事例と業務効率化の効果
- ・AI文字起こしツールを選ぶ際のポイント
- ・主要なAI文字起こしツール10製品の紹介
- ・Notta:世界4大デザイン賞を受賞した実力
- ・LINE WORKS AiNote:旧CLOVA Noteβの法人版
- ・YOMEL:ワンクリックで議事録作成
- ・toruno:議事録作成の手間を削減
- ・ZMEETING:産総研発のAI音声認識技術
- ・PLAUD NOTE:高度AI連携 ボイスレコーダー
- ・amptalk:商談や電話の会話に
- ・Jamroll:様々なツールと連携可能
- ・Google ドキュメント 音声入力
- ・Whisper:OpenAIの音声認識モデル
- ・ChatGPTで文字起こしはできる?
- ・有料・無料プランと費用目安
- ・AI文字起こしを使いこなすコツ
- ・注意すべきセキュリティ・プライバシー対策
- ・AI文字起こしならABKSSにご相談ください
AI文字起こしとは?

AI文字起こしは、音声や動画の内容を自動でテキスト化する仕組みです。
音声認識エンジンが音波を解析して文字に変換する技術で、近年はディープラーニングの進化により、雑音やアクセントの違いにも強くなりました。多言語に対応したサービスも増え、グローバルでの活用も進んでいます。
作業の手間を減らせることから、記録や字幕作成などの効率化に役立ちます。特に長時間の会議や講演をテキストで残せば、後から情報を検索しやすくなるメリットがあります。
今や多くの現場で、AI文字起こしは欠かせない技術となっています。
文字起こしのしくみとAI技術の進化
AI文字起こしは、音声波形をコンピュータが理解できる形に変換する技術が基盤です。
ディープラーニングによってノイズや話者の癖にも対応し、精度の高い認識が可能になっています。最近では、話者の識別や専門用語への対応力も強化されています。
また、自然言語処理の導入により、文脈を理解して自然な文章に整える要約ツールも登場。
こうした技術の組み合わせによって、AI文字起こしの性能は大きく向上し、さまざまな分野で活用されています。
音声・動画データをテキスト化するメリット
音声・動画データをテキスト化することで、キーワード検索が可能になり、必要な情報を迅速に抽出できます。
また、会議録やインタビューの整理、字幕作成の効率が大幅に向上するなど、業務の時短にも貢献します。
さらに、テキスト化されたデータは社内のナレッジ共有や顧客対応の記録、マーケティング分析などにも活用でき、情報の再利用や資産化がしやすくなる点も大きなメリットです。
導入事例と業務効率化の効果
個人での利用:ブログ、字幕作成、学習ノートなど

個人がAI文字起こしを活用する主な場面としては、取材内容のテキスト化やYouTube動画への字幕作成が挙げられます。
音声を取り込むだけで必要な文章を得られるため、タイピングによる労力や時間を大幅に削減できます。特に複数言語に対応しているツールを使えば、海外向けのコンテンツ作成への応用もしやすいでしょう。
また、セミナーや講演を録音して学習ノートを作成する方法も有用です。録音された内容をAI文字起こしツールでテキスト化すれば、後から内容を復習しやすくなり、学習効率が上がります。
企業・チームでの利用:議事録、マニュアル、研修資料など

企業やチームでは、会議や電話会議などでの議事録作成が最も広く導入されています。
議事録は情報共有や意思決定プロセスの可視化に不可欠ですが、手動での作成には時間がかかります。そこでAI文字起こしを活用することで、会議終了後すぐに参加者へ配布することが可能です。
また、マニュアル作成や研修動画のテキスト化に応用することで、資料作成の手間や内容の抜け漏れを防ぎやすくなります。録音データを蓄積・分析できる点も魅力で、企業が持つナレッジ資産を積極的に活用できる仕組みとして注目されています。
AI文字起こしツールを選ぶ際のポイント
数多くのAI文字起こしツールが存在する中で、最適なものを選定するには以下のポイントに注意するようにしましょう。
対応言語や精度
ツールによって対応している言語の種類や認識精度には差があります。
特に専門用語の処理能力や複数話者の識別精度は、業務利用では重要なポイントになります。日本語対応の正確さに加え、音声が曖昧でも高精度で文字に変換できるかをチェックしましょう。
操作の簡単さ
日常的に使用するツールだからこそ、操作のしやすさは非常に重要です。直感的に使えるUIかどうか、また非IT系の方でもスムーズに扱える設計になっているかを確認しましょう。
保存や共有機能
作成した文字データを安全に保存し、関係者と共有できる機能は業務効率に大きく関わります。
クラウド保存対応の有無や、共有リンクの発行、編集履歴の追跡機能などが整っているかをチェックしましょう。
料金プランの柔軟さ
無料プランの範囲でどこまで使えるか、有料プランに移行した際にどのような機能が追加されるかを把握しておくことも大切です。
自分の利用頻度や目的に見合ったコストかどうかを見極めるため、月額・年額・従量課金制などプラン体系も比較して選びましょう。
利用シーンとの相性
文字起こしツールは、利用シーンに応じて選ぶべき機能が異なります。
たとえば会議であれば話者を区別できる機能、セミナーや講義の記録には要点を自動でまとめてくれる機能が役立ちます。
どのような場面で使うのかをはっきりさせておくことで、最適なツールの見極めがしやすくなります。
主要なAI文字起こしツール10製品の紹介
AI文字起こしツールの中から代表的な10製品を、「会議向け(会議・ミーティングの議事録を効率化したい)」「営業向け(営業・商談の会話を記録・活用したい)」「個人利用向け(個人・小規模利用に適した音声入力) 」に分類して紹介します。
それぞれ機能や強みに違いがあるため、目的や環境に合ったものを選ぶには、無料トライアルの活用がおすすめです。
会議向け |
営業向け |
個人利用向け |
■会議・ミーティングの議事録を効率化したい人向け
Notta:世界4大デザイン賞を受賞した実力
Nottaはシンプルかつ直感的なユーザーインターフェースが特長で、初めてAI文字起こしを使う方でもすぐに利用できます。
法人向けの大規模プランがあり、データ取り扱いのセキュリティやサポート体制も充実しているため、チームや企業規模での導入にも適しています。
- リアルタイム文字起こしと翻訳機能を搭載
- AI要約機能で生成されたテキストから要点を抽出し、瞬時に要約を作成
-
スマートフォンアプリ、Chrome拡張機能、Webアプリなどに対応
LINE WORKS AiNote:旧CLOVA Noteβの法人版
LINE WORKS AiNoteは、累計登録者100万人の「CLOVA Note β」の法人版としてリリースされた文字起こしツールです。
会議音声を自動で文字起こし・要約し、LINE WORKS上で簡単に共有できます。フリープランもあり、気軽に導入可能です。
- AIが会話をリアルタイムで文字起こし・自動要約
- 話者ごとの識別やタイムスタンプ付きで確認しやすい
-
LINE WORKSと連携し、議事録の共有・活用がスムーズ
>>「LINE WORKS AiNote」に関するお問い合わせはこちらから
YOMEL:ワンクリックで議事録作成
YOMELは「会議が終われば即議事録が完成する」という使い勝手の良さが支持されています。
録音からテキスト化だけでなく、要点をまとめたレポートを自動生成する機能があるため、議事録作成の手間を大幅に省けます。
- ワンクリックで簡単に議事録作成を開始・終了できる。
- 話者分離や要約、不要部分の削除を自動化。
-
リアルタイムで会話を確認できる。
toruno:議事録作成の手間を削減
torunoはWeb会議で使用することを想定した文字起こしサービスで、オンライン会議ツールとの連携がスムーズです。
録画や録音内容を取り込み、ほぼリアルタイムでテキスト化してくれます。
- リアルタイムでの文字起こし機能
- 録音と画面キャプチャ機能を同時に利用可能
-
最大9割以上の精度で文字起こしが可能
ZMEETING:産総研発のAI音声認識技術
ZMEETINGは、産業技術総合研究所が開発に携わった高精度の音声認識技術を採用しています。
国内の研究成果を応用していることから、企業や公共機関からの信頼度も高く、セキュリティ面やサポート体制が充実しています。
- 音声認識率90%以上の高精度AI搭載。
- アカウント作成は無制限で、時間単位の課金制を採用。
-
暗号化通信やアクセスログ監視、認証機能。
■営業・商談の会話を記録・活用したい人向け
PLAUD NOTE:高度AI連携 ボイスレコーダー
PLAUD NOTEは、専用のハードウェアを活用したボイスレコーダーとAIを組み合わせることで、音声の録音から文字起こし、要約までの一連のフローをスムーズに実行できる製品です。
薄型で携帯性に優れ、外出先での講演や取材の録音にも適しています。
文字起こしおよび要約の精度は非常に高く、会議やインタビュー、講演などの重要な記録も安心して任せられます。
さらに、収録したデータはスマートフォンやクラウドと連携して即時に確認・共有でき、PCレスでも高効率な業務運用が可能です。
従来のICレコーダーでは実現できなかった「録る・書き起こす・まとめる」を1台で完結する革新的なソリューションです。
- ワンタッチでいつでもどこでも瞬時に録音開始
- 世界4大デザイン賞を全て受賞
- 最新GPT&ClaudeによるAI文字起こし&超高精度要約
>>「PLAUD NOTE」に関するお問い合わせはこちらから
amptalk:商談や電話の会話に
amptalkは通話録音を自動的にテキスト化してくれるサービスとして、営業現場などで重宝されています。
特に電話サポートやテレアポなど、音声によるコミュニケーションが中心となる業務で大きな効果を発揮します。
- ビデオ会議やIP電話の録音データをAIが自動で解析可能。
- AIが書き起こし内容を要約し、SFAやCRMに自動入力。
-
会話内容をAIが分類し、ヒアリングや予算などのトピックごとに整理。
Jamroll:様々なツールと連携可能
Jamrollは他のクラウドサービスやデータ分析ツールとの連携がしやすいのが特長です。
APIを介して自動的にテキストデータを取得し、会議分析や要約レポートを自動生成するなど、ワークフローに合わせた拡張が自在にできます。
- 商談の録画データをAIが解析し、話し方や顧客反応を可視化。
- 営業戦略の改善や成約率向上を支援。
-
AIが商談内容を要約し、TODOタスクやBANTCH情報を自動抽出。
■ 個人・小規模利用に適した音声入力ツール
Google ドキュメント 音声入力
Google ドキュメントに搭載されている音声入力機能は、無料で利用できる手軽さが最大の魅力です。
マイクを使いリアルタイムで文字起こしが行われるので、スピーチやメモ代わりに使うこともできます。Googleアカウントがあればすぐに試せるため、初心者がAI文字起こしを体験する導入手段としてみてはいかがでしょうか。
- Googleのパワフルな音声認識エンジンを活用
- ブラウザから直接アクセス可能で追加インストール不要
- 完全無料で利用可能
Whisper:OpenAIの音声認識モデル
WhisperはOpenAIがオープンソースとして公開している音声認識モデルで、多言語対応と高い認識精度が特長です。
API版の「whisper-1」は処理した音声ファイルの時間に応じて課金されますが、GitHub版は無料で利用できます。
- 68万時間もの多言語音声データで学習した高精度な認識能力
- 日本語を含む多言語に対応
- オープンソース版と API版が提供されている
ChatGPTで文字起こしはできる?
ChatGPTは音声データを直接文字起こしする機能は備えていません。
つまり、録音データや会議音声をアップロードしてそのままテキスト化することはできないのです。文字起こしを行うには、先述した専用のAI文字起こしツールとの併用が前提となります。
ChatGPTは「文字起こし後の整理」に最適
文字起こしが済んだテキストをChatGPTに渡すことで、「要点をまとめて」「議事録風に整えて」「話し言葉を文章に直して」といった使い方ができます。
これは会議録やインタビューの内容を分かりやすく整理したいときに特に便利です。音声の変換は専用ツール、整形や要約はChatGPTと役割分担するのが効率的でしょう。
有料・無料プランと費用目安

AI文字起こしツールの料金は、月額制や録音時間ごとの従量課金制など様々です。中には、無料プランで基本機能を試せるサービスも多く、導入コストを抑えて始めることも可能です。
ただし、録音データが多い場合は無料枠を超えるため、有料プランの検討が必要です。必要な機能に合わせて、最適なプランを選びましょう。
サブスクリプションプランと無制限利用の可能性
サブスクリプション(定額制)プランでは、一定の録音時間や機能を月額・年額で利用可能です。
議事録作成や長時間インタビュー、講義・研修の記録など、音声を頻繁に扱うユーザーにとってはコスト管理がしやすく、導入しやすいのが特長です。
特に、1回の録音が長時間に及ぶメディア関係者や、日常的に会議がある企業では、録音時間に制限のない無制限プランの方がコストパフォーマンスに優れるケースも多いこともあります。使用イメージに合わせて検討するようにしましょう。
1分あたりのコスト試算と導入コスト
従量課金型では、1分あたり数円~十数円といった価格設定が多く、短時間の利用であれば低コストです。ただし長時間の音声を頻繁に扱うなら、定額制の方が割安になるかもしれません。
単純なコスト比較だけでなく、業務効率化や人件費削減といった導入効果も加味することで、最適なプランが見えてきます。
AI文字起こしを使いこなすコツ

音声をクリアに録音する
録音は静かな環境で行い、マイク使用時は風切り音や振動に注意しましょう。雑音が少ないほど、AIの文字起こし精度は高まります。
音質も重要で、機器の性能やマイクレベルの調整によって、誤変換のリスクを減らせます。
話者ごとに話すタイミングを意識する
複数人が同時に話すとAIは混乱しやすいため、発言のタイミングをずらすと精度が向上します。
司会が発言を整理したり、話者が交代する時に間を取るなどの工夫も効果的です。話者識別機能がある場合も、発言を明確に区切ることで認識が安定します。
専門用語は辞書登録・事前学習させる
医療やITなど専門分野では誤変換を防ぐため、専門用語や社内用語を辞書に登録しておくと安心です。これにより修正作業の手間が減り、精度の高いテキスト化が可能になります。
注意すべきセキュリティ・プライバシー対策
機密情報を扱う場合は利用規約を確認
ツールごとにデータの扱いが異なるため、契約前に利用規約を確認しましょう。
特に、録音データの所有権やアクセス範囲について明確にしておく必要があります。不明点があれば問い合わせておくと安心です。
信頼できるツールを選ぶ
ISO27001やSOC2などの認証を取得しているかを確認することで、信頼性を判断しやすくなります。セキュリティ情報が明示されているツールは、社内での運用もしやすいです。
ISO 27001:情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格。 企業の情報保護体制が整っている証明。
SOC 2:米国公認会計士協会が策定したフレームワークで、サービス提供者のセキュリティや法令遵守体制を5つの基準で評価する仕組み。
データの保管・削除ルールを徹底
長期保存は漏えいリスクになりえます。自動削除機能の有無や、手動での削除が簡単にできるかを確認するようにしましょう。運用に応じた設定が可能かも重要です。
AI文字起こしならABKSSにご相談ください
AI文字起こしツールは数多く存在し、選定に迷う方も多いのではないでしょうか。ABKSSでは、最適なツールの選定から導入後の運用サポートまで丁寧に支援しています。
自社に合ったツールの選定から実装後の運用サポートまで総合的にサポートしますので、新たにAI文字起こしを導入したいと考えている方や、既存ツールの乗り換えを検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
▼まずは資料をダウンロード!
この記事で紹介しているAI議事録作成ツールの詳細比較や選定ポイントをまとめた資料をご用意しました。 無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。