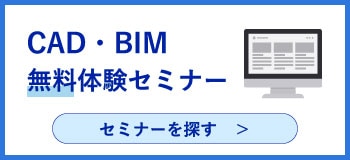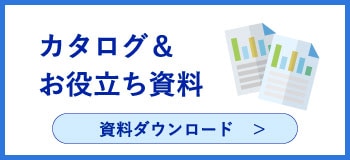デジタルツインとは?意味や特徴をわかりやすく解説

近年、IoTや5G、AIなどのテクノロジーが急速に進化し、物理空間とサイバー空間をつなげる取り組みが多くの分野で注目されています。製品開発や社会インフラの整備においても、現実空間のデータを活用した高度な分析や予測が求められるようになりました。
そうした背景の中で、実空間をコンピュータ上にほぼそのまま再現し、リアルタイムで連携・分析を行う「デジタルツイン」は特に大きな注目を集めています。製造業や建設業、都市計画、医療といった幅広い産業分野で、効率化や品質向上に役立つ有望な技術として期待されています。
本記事では、デジタルツインの定義や特徴をはじめ、その実現を支える技術要素や導入のメリット・課題についてわかりやすく解説します。
このような方におすすめの記事です
- デジタルツインの基礎を学びたい方
- デジタルツインの導入メリットと課題を整理したい方
- 建設や製造でDXを進めたい方
- 不動産や都市計画に携わる方
デジタルツインの基本情報

デジタルツインとは
「デジタルツイン」とは、現実世界のモノや環境をサイバー空間に再現し、データと連携しながらリアルタイムに近い形で監視・分析・シミュレーションを行う技術です。
センサーやIoT機器から集めた情報を5G通信やAI解析と組み合わせることで、現実の変化が即座にデジタルモデルへ反映されます。そのため、設備や街の構造などを仮想空間で正確に把握でき、モニタリングや予測を効率的に実施可能です。
これにより、試作や実験を繰り返さなくても改善点や最適な解決策を探ることができ、製品開発やシステム運用におけるコスト削減や効率向上につながります。
デジタルツインが注目される理由
デジタルツインが注目される背景には、IoTや5Gなど通信技術の進化が大きく関係しています。以前はデータ量や通信速度の制約でリアルタイム化が困難でしたが、今はセンサーで取得した膨大な情報をクラウドに瞬時に送信・分析できるようになりました。
また、AIの進化によってビッグデータから高精度な予測モデルを作成できるため、リスク低減や効率化など具体的な成果を生みやすくなっています。
シミュレーションとの違い
従来の「シミュレーション」は、過去の実測データや想定条件をもとに将来を仮定する手法が主流で、予測精度や再現性に限界がありました。
一方で、「デジタルツイン」は実際の運用データをリアルタイムで反映します。
これにより、実環境とバーチャル空間の状態が常に同期されるため、シミュレーション結果に対する即時的なフィードバックと改善が可能になるのです。
メタバースとの違い
「メタバース」は、ユーザー同士が仮想空間で交流することや、新しい仮想世界を創造することに重点があります。
一方で「デジタルツイン」は、あくまでも現実世界の再現を目的としており、実空間からのデータを忠実に取り込むことで現実とほぼ同じ環境を作り出す点が大きな違いです。
意思決定を行うための正確なシミュレーションや予測にデジタルツインを活用しつつ、そこにエンターテインメント要素を加える目的でメタバース的技術を組み合わせるケースも今後増えると考えられています。
デジタルツインの活用を支える技術

IoTと5Gによるリアルタイムデータ連携
IoTは、センサーやアクチュエーターといったデバイスをネットワークで結び、さまざまな情報を取得・送信する仕組みです。
これに5Gの大容量・低遅延通信が組み合わさることで、現地で起こった変化をほぼ瞬時にクラウドへ送信し、仮想空間への反映が可能になります。
たとえば、工場の稼働データをリアルタイムで収集することで、生産ラインの稼働状況を常に把握し、不具合や在庫状況の変化に即座に対応するといったことが可能になります。
AIを活用した高度な分析と予測
IoTで収集された膨大なデータを分析し、人間の手では見つけにくいパターンや兆候を発見するのがAIの強みです。
たとえば、機械学習やディープラーニングを用いることで、設備の故障が起きる前に異常値を検知し、メンテナンスの時期を予測するといった高度な予知保全が可能となります。
蓄積されたデータが多いほどAIは学習精度を高めるため、デジタルツインとの相乗効果で予測やシミュレーションの精度を格段に上げることができると考えられます。
VR・ARによる可視化と操作性の拡張
VR(仮想現実)や AR(拡張現実)の技術を導入することで、ユーザーはデジタルツインの世界を視覚的にチェックし、操作しやすい形で情報を得ることができます。
たとえば、VR技術を使って工場内のレイアウトを体験すれば、設備の配置を最適化するシミュレーションを容易に行うことが可能です。
また、AR技術を使えば、実際の現場に仮想情報を重ねて表示しながら、リアルタイムの稼働状況を可視化してメンテナンスをガイドするなど、直感的なモニタリングや作業支援を実現することもできるでしょう。

▼VR技術の活用にはVRゴーグルが不可欠です。Meta Questは多くの分野で活用が進む注目のデバイスです。
デジタルツインのメリット

コスト削減と効率化
デジタルツインは、物理的に新しい試作品を作る前に仮想空間で実験が行えるため、材料費や人件費を大きく削減できます。生産ラインの設計変更を繰り返す場合でも、実作業を始める前にデジタル上でシミュレートして最適解を導き出せるので、効率化が進みます。
結果として、開発のスピードアップとコスト圧縮を同時に推進することが可能です。
品質向上とリスク低減
デジタルツイン上で製品やプロセスの挙動をリアルに模擬できるため、潜在的な不具合やリスクを初期段階で洗い出すことができます。不良品やシステム障害などが起こる前に対策を講じられるため、品質向上や納期遵守に役立ちます。
また、シミュレーションの結果を積み重ねてビッグデータを形成することで、さらなるリスク低減や品質改善への改善案を絶えず検証できます。
遠隔モニタリングと予知保全
地理的に離れた場所からでも設備や機器の稼働状況を把握し、トラブルが起きそうな箇所を事前に解析できるのは大きなメリットです。
万が一異常が起こる場合も、早期対応が可能になるためダウンタイムを最小限に抑えることが期待できます。
こうした予知保全の仕組みは、従来の定期点検とは違い、実データに基づいたタイミングでメンテナンスを行うため、工数やコストの最適化にも貢献します。
デジタルツインのデメリット・課題

導入コストと専門人材の確保
最先端の技術を駆使するデジタルツインの構築には、センサーの設置・運用、AIモデルの開発、ネットワーク環境の整備など多面的な投資が必要です。
特に大規模なシステムを扱う場合、専門知識を持ったエンジニアやデータサイエンティストの育成・確保も課題となります。導入効果を得るまでのスパンが長期化する可能性もあるため、戦略的な投資判断が求められます。
データプライバシー・セキュリティの懸念
リアルタイムで取得されるデータが増えるほど、情報漏洩や不正アクセスなどのリスクも高まります。個人情報を含む場合には、プライバシー保護も重要な検討事項となるでしょう。
システム全体の安全性を確保するために、暗号化やアクセス制御、法規制の遵守など複数の対策を並行して行う必要があります。
デジタルツインの活用事例
1.設備稼働の最適化
発電設備や空調機器の分野では、タービンや大型空調設備に取り付けられたセンサーから稼働データをリアルタイムで収集し、デジタルツイン上で解析する取り組みが進んでいます。
温度や振動の異常値を検知すると、運転を止めることなく予防的にメンテナンスを実施でき、突発的な故障や長時間の稼働停止を回避可能です。
その結果、修理コストの削減だけでなく、安定した設備運用やエネルギー効率の最大化にもつながっています。
2.都市3Dモデルの整備
国土交通省が進める「PLATEAU」プロジェクトでは、日本全国の都市を3Dモデルとして整備し、防災や街づくり、新たなサービス開発に生かす取り組みが進行中です。
現土地形や建物のデータをもとに、災害リスクの予測や渋滞シミュレーションなどを高精度で行い、行政施策や地域活性化の検討に活用されています。
さらに東京都では「デジタルツイン実現プロジェクト」を独自に展開し、防災対策や都市の混雑状況のリアルタイム把握、都市計画への活用を進めています。
参照:国土交通省「PLATEAU」プロジェクト|https://www.mlit.go.jp/plateau/
参照:東京都「デジタルツイン実現プロジェクト」|https://info.tokyo-digitaltwin.metro.tokyo.lg.jp/
3. 施工管理と安全対策
大手ゼネコンでは、建設現場を丸ごと3Dモデル化し、作業員や重機の動線まで含めたシミュレーションを行っています。
たとえば、クレーンの稼働範囲や資材搬入のタイミングを事前に検証することで、工程の遅れや現場での接触事故を未然に防止することが可能です。
進捗状況もデジタル上でリアルタイムに可視化できるため、工期短縮や施工品質の向上にも大きく貢献しています。
4. 災害発生前の被害範囲の予測
内閣府が推進する「CPS4D」では、地震や洪水、津波といった災害を想定したシミュレーションをデジタルツイン上で実施しています。
地形データや建物配置、人口分布など反映させることで、どの地域にどれだけの被害が及ぶかを事前に予測することが可能です。
これにより避難経路の設計や救援物資の配置をあらかじめ検討でき、自治体の迅速な対応と市民の安全確保に役立っています。
5.サッカーの試合データをリアルタイムで取得
デジタルツインでサッカー試合のデータをリアルタイムに取得すると、選手やボールの位置やスピードを瞬時に仮想空間へ反映できます。観戦者は画面上でフォーメーションや動きの変化を直感的に把握でき、監督やコーチは即座に戦術を検討可能です。
さらに、走行距離や加速度といった負荷データを分析することで、選手のコンディション管理やケガ予防、パフォーマンス改善にも活用されています。
Matterportを活用した現場データの3D化
Matterportは、建物や空間を高精度に3Dスキャンし、デジタル上で「そのまま歩けるような」モデルを生成できるサービスです。
この技術をデジタルツインに活用すると、実際の建物の状態をリアルに再現しつつ、点検・改修・レイアウト検討などを仮想空間で行うことが可能になります。つまり、Matterportは「実空間をデジタルツイン化する入口」として役立つツールだと言えます。
Matterportとは
Matterportは、専用カメラやスマートフォンを用いて建物内部を3Dスキャンし、没入感のあるデジタルモデルを生成するプラットフォームです。撮影した空間はクラウド上に保存され、PCやスマートフォンから誰でも自由に歩き回るように閲覧できます。
さらに、サイズ測定やタグ付け、共有リンクの発行といった機能も備えており、不動産・建設・施設管理など幅広い分野で活用されています。
実際の現場をそのままデジタル空間に再現できるため、遠隔での確認や打ち合わせ、メンテナンス計画の効率化に大きな効果を発揮します。
Matterportカメラなら正規販売代理店のABKSSへ

ABKSSはMatterport正規販売代理店として、機材選定から導入後の活用サポートまで一貫して対応します。撮影代行や運用相談も可能ですので、安心してご導入いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
おわりに
デジタルツインは社会やビジネスを大きく変革する可能性を秘めています。導入コストや人材確保といった課題はあるものの、活用できれば生産性向上やリスク低減など大きな効果が期待できます。
現実とサイバー空間を緊密に連携させる重要性は今後さらに高まり、企業や官公庁でも研究・実用化が進んでいます。こうした中、Matterportのように空間を手軽に3D化できるサービスは、デジタルツイン実現への身近な一歩として注目を集めています。
Matterportの導入や活用のご相談は、ぜひABKSSへお任せください。
▼現場で撮影された、Matterportによる3Dデータサンプルをご覧いただけます(無料)。画面上を自由に歩き回れるウォークスルー形式で、圧倒的な再現性と臨場感をぜひ体感してください。
こちらの記事もおすすめです